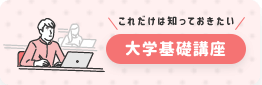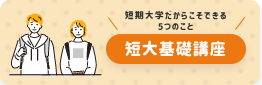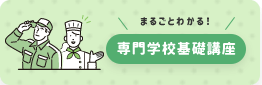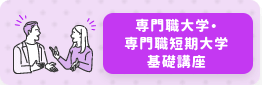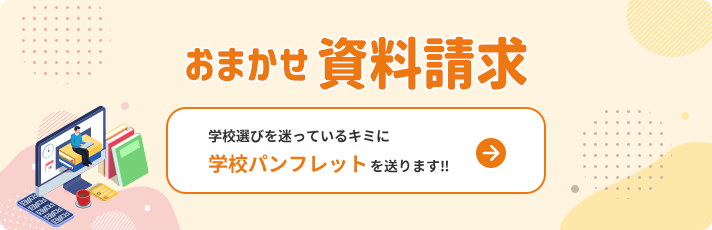専門学校の奨学金ってどんな種類があるの?
奨学金とは
奨学金とは「経済的な理由で修学が困難な学ぶ意欲のある学生」の学費を経済的に支援する制度です。代表的な日本学生支援機構の奨学金の場合、大きく分けると返済しなければならない「貸与型」と、2020年に大改革を行い高等教育の無償化支援新制度に組み込まれた「給付型」とがあります。さらに申込時期も、高校在学中に申込を行い専門学校の入学後の4月以降から支給される「予約採用」と、専門学校の入学後に申込を行い7月頃から支給される「在学採用」があります。
⇒ 予約採用(日本学生支援機構HP)
⇒ 在学採用(日本学生支援機構HP)
貸与型奨学金の仕組みについて
ここでは、多くの学生が利用している日本学生支援機構の貸与型奨学金の仕組みについてご紹介します。 貸与型奨学金は2種類あり、利子がある第二種奨学金と、利子がない第一種奨学金があります。いずれも在学中には返済する必要がなく、その間は第二種も利子も発生しません。貸与されるのは予約採用でも専門学校入学後の4月以降。つまり、入学金の支払いには間に合わないため注意が必要です。また、貸与は振込で行われますが、原則として卒業まで続くものの、毎年「奨学金継続願」の提出も必要です。この継続願の内容をもとに学校は、学業はもちろん、人物、健康、経済状況などの審査を行い奨学金の継続を決めます。長期間の欠席や、成績が著しく低下しているなど問題がある場合は奨学金が停止されることもあります。返済は卒業後7か月目に開始しますが、第二種の利子は返還完了まで金利が一定の「利率固定方式」と、5年ごとに金利を見直す「利率見直し方式」があります。また所得連動返還型奨学金制度(後述)も用意されています。
また、貸与型奨学金を利用する場合には、人的保証あるいは、機関保証を利用することになります。人的保証は、契約者本人と同等の返済義務を負う連帯保証人と、契約者・連帯保証人の次に返済義務を負う保証人の両方を立てる必要があります。日本学生支援機構の奨学金では、契約者は奨学金を受ける学生本人となりますから、連帯保証人は父母がなることが多いでしょう。
人的保証は連帯保証人だけでなく保証人も必要なことから、機関保証を選ぶ人も少なくありません。この場合は、連帯保証人・保証人を立てる必要はなく、保証機関である「日本国際教育支援協会」に保証金を支払います。保証金の額は、貸与額に応じて異なりますが、第一種奨学金で私立・自宅から通う場合、月額の貸与額が4万円の場合で1,032円が必要となります。毎月振込される奨学金から自動的に保証金が差し引かれる仕組みです。「所得連動返還型奨学金制度」の場合は、機関保証のみとなります。
| 区分 | 貸与金額(月額) | ||
|---|---|---|---|
| 自宅通学者 | 自宅外通学者 | ||
| 第1種 (無利子) |
国公立 | 2万円・3万円・4万5000円 | 2万円・3万円・4万円・5万1000円 |
| 私立 | 2万円・3万円・4万円・5万3000円 | 2万円・3万円・4万円・5万円・6万円 | |
| 第2種 (有利子) |
2万円~12万円まで1万円単位で選択 | ||
対象学科と学力基準について
専門学校へ進学するにあたり、日本学生支援機構の奨学金の利用を希望する際は、「対象学科」と「学力基準」を必ず確認しておきましょう。
対象学科は、日本学生支援機構のHPで地域別に紹介されています。
⇒ 奨学金対象学科を確認する
学力基準は、申し込むタイミングと希望する奨学金によって異なります。
例えば、予約採用で貸与型の第1種の奨学金を希望する場合は、特別な条件を満たさない限り、高等学校または専修学校高等課程の1年から申し込み時までの成績の平均が3.5以上でなければなりません。在学採用で申し込む場合は、高等学校または専修学校高等課程における最終2か年の成績の平均が3.2以上であることなどが必須条件となります。
学力基準以外に、世帯人数と収入金額が選考の対象になる「家計基準」もあるため、希望する奨学金の採用基準はあらかじめ確認しておきましょう。
| 無利子貸与(第一種) | 有利子貸与(第二種) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 世帯人数 | 3人 | 4人 | 3人 | 4人 | |
| 収入金額 | 給与所得者 | 716万円以内 | 803万円以内 | 1,113万円以内 | 1,250万円以内 |
| 給与所得以外 | 536万円以内 | 552万円以内 | 879万円以内 | 892万円以内 | |
奨学金の返済方法
貸与型奨学金の返済方法は「口座振替」のみです。奨学金利用者が指定した金融機関の預・貯金口座から、毎月決まった額が自動引き落としされます。具体的な割賦方法は「月賦返還」と「月賦・半年賦併用返還」の2種類があり、自由に選択できます。
月賦返還は毎月決まった額を返済する方式で、返済が始まるのは貸与期間終了の翌月から数えて7か月目の27日(金融機関が休日の場合は翌営業日)からです。その後、毎月27日が返済日になります。
月賦・半年賦併用返還は返済金を2つに分け、1つは月賦返還で返済し、もう1つは半年賦返還で返済する方式です。月賦返還での返済については、上記でご紹介した内容と変わりありません。半年賦での返済については、半年賦返還で返済する金額をさらに2つに分け、1月と7月(ともに27日)に返済します。つまり、1月と7月だけ月賦返還と半年賦返還、両方の方式で返済するということです。
なお、半年賦返還の1回目の振替日は、貸与期間終了の翌月から数えて6か月経過後の1月または7月のどちらか早い月の27日です。

受給までのスケジュールは?
貸与型奨学金&高等教育の進学支援新制度
<予約採用(進学前)>
- 申込(4月下旬~)
- 通知(10月~)
- 入学(4月~)
<在学採用(進学後)>
- 申込(4月~)
- 推薦(申込後)
- 受給開始(7月~)
種類豊かな支援制度をうまく活用しよう
その他の主な奨学金制度
高等教育の修学支援新制度について
従来の給付型奨学金に加えて授業料や入学金が減免・免除される制度として、 2020年度から「高等教育の修学支援新制度」がスタートしました。ただ、家庭の経済状況や世帯構成など細かな採用基準があるうえ、進学する学校が制度対象校ではない場合は、利用できません。早めに確認しておくことが大切です。
⇒ 文部科学省「高等教育の修学支援新制度」特設ページ
日本学生支援機構以外の奨学金について
学校の中には独自に奨学金制度を設けているところがたくさんあります。貸与型に給付型、金額もさまざま。成績や経済状況が条件となる場合が多いです。また入試や在学中の成績で特典が受けられる「特待生制度」などもあります。その他、学生が居住している地方公共団体などで奨学金制度を設けている場合もありますので調べてみてください。また新聞奨学生など、民間の奨学金制度もあります。ただし、日本学生支援機構の奨学金と併用できないものもあります。
奨学金を受けるためには
奨学金を受けるためには、自分の条件とマッチする奨学金制度を見つけるのが先決です。学校単位で受け付けている奨学金はもちろん、さまざまな奨学金の情報を集めることも大切。特に貸与型の奨学金であれば、契約し返済するのは自分自身です。受け身の姿勢ではなく、自分から情報を取りにいきましょう。
高校在学中に申込を行い専門学校の入学後の4月以降から支給される「予約採用」を受けたい場合は 、高校3年生になる前からチェックしておきましょう。詳しくは「②受給までのスケジュールは?」を参照してください。またこうした制度は、専門学校などが独自に用意している場合もあります。進学したいと考えている学校に、奨学金制度がないかの確認も忘れずに行いましょう。学校独自の予約型奨学金の多くは、返済の必要がない給付型奨学金が多く、卒業後に返済に追われる心配もありません。成績など学校独自に設定していますが、受給資格があるのであれば、ぜひ申請しましょう。
オープンキャンパスなどのカウンセリングで相談すると条件の説明やアドバイスをもらえます。奨学金のパンフレットだけでは分からない部分についても教えてもらえることがありますから、積極的に相談してみましょう。

教育ローン
教育ローンの長所・短所とは?
成績にほとんど左右されずに借りられる点と、一度に最大数百万円の大きな金額を借りられる点がメリット。ただし、奨学金に比べ、利息が高いのがデメリット。大抵の奨学金の場合、お金の支給は入学後からとなるので、入学前の納入金を用意したいとき、有効な手段です。
そんな教育ローンには、日本政策金融公庫が提供する「国の教育ローン」と「銀行や信用金庫、信販会社の教育ローン」があります。
日本政策金融公庫(国の教育ローン)
国の教育ローンは、最高で350万円まで利用できます。金利は固定金利で、年2.35%(令和6年12月時点)です。受験前でも申し込み可能で、早ければ20日程度で融資を受けられます。入学金を支払う前に振り込みが完了するため、入学金はもちろん、一人暮らしの住居費用やパソコン購入費などに充てられます。なお、日本学生支援機構の奨学金との併用も可能です。
銀行や信用金庫、信販会社の教育ローン
銀行の教育ローンは入学金のほか、予備校や塾など教育に関わる資金に利用できます。ただし、金利は国の教育ローンよりも高めに設定されているケースがほとんどです。同じ銀行の教育ローンでも地域によって金利や借入可能額、返済方法は異なるため、最寄りの銀行で確認しましょう。
代表的な奨学金・教育ローンの比較
| 制度名 | 区分 | 審査基準・条件 | 貸与・支給額 | 卒業後の 返済月額 |
返済年数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奨学金 | 日本学生支援機構奨学金 | 第一種: 無利子貸与 第二種: 有利子貸与 |
第一種は評定平均3.5以上(予約採用)、または3.2以上(在学採用)。 家計の基準額は、世帯人数、就学者の有無などによって異なる |
第一種:2万~6万円/月 第二種:2万~12万円/月 |
例:(第二種奨学金月額5万円×2年、年利0.940%で貸与した場合)定額返還12年で8,853円 | 9~20年(第一種・第二種、修業年限、貸与月数により異なる) |
| 東京都育英資金 | 無利子貸与 | 都内の専門学校に在学しており、申込者とその保護者が都内に在住していること など | 国公立:4万5千円/月 私立:5万3千円/月 |
例:(月額5万3千円×2年で貸与した場合)13年返還で8,150円 | 11~15年(金額によって異なる) | |
| あしなが育英会奨学金 | 無利子貸与 | 保護者が病気や災害などで死亡、あるいは後遺障害のため働けず教育費に困っていること | 4万円/月 | 例:(月額4万円を2年間貸与した場合)20年返還で4千円 | 最長20年 | |
| 学校独自の奨学金 | 給付・貸与両方あり | 学校により異なる | 学校により異なる | 学校により異なる | 学校により異なる | |
| ローン | 教育ローン (日本政策金融公庫の場合) |
有利子貸与 | 申し込みの家計基準は世帯の人数により異なる。 世帯年収の上限額(例:子ども一人の家庭:最高990万円、二人の家庭:最高990万円、三人の家庭:990万円) |
最大350万円までで任意の額(一定の条件を満たせば450万円まで融資可能) | 例:(120万円・在学中は元金の返済無しで貸与した場合)15年返済で8,000円 | 最長18年 |
※このデータは(株)さんぽうが独自に調査したものであり、後日、内容などに変更が生じる可能性があります。
奨学金増額貸与&返済支援制度
入学時特別増額貸与奨学金制度
入学時特別増額を利用するには、2つある条件のうち、いずれか1つを満たす必要があります。
1.奨学金申請時に家計基準における認定所得金額の評価が0になる人
2.日本政策金融公庫が提供する「国の教育ローン」の利用ができず、国の教育ローン借入申込書のコピー、または融資できない旨を示した公庫が発行する通知文のコピーを提出した人
入学時特別増額を希望する際は、必ず第一種または第二種と合わせて申請する必要があります。入学時特別増額のみの申請はできないので、注意しましょう。また、入学時特別増額が貸与されるのは入学後です。原則、入学費用に充てることはできないので、覚えておきましょう。
所得連動返還型奨学金制度
これまで日本学生支援機構奨学金の無利子貸与(第一種)では、一定額を月々返済していく「定額返還型」しかなく、新社会人である奨学金利用者にとって負担の大きいものでした。そこで、もう一つの選択肢として始まったのが「所得連動返還型奨学金制度」です。
最大の特徴は、年収に応じて返す月額を決められるところです。所得が少ない時期は返済額も少なくなるので、無理なく返済できます。一方で所得が一定額を超えると、定額返還型よりも返済月額が多くなります。所得連動返還型と定額返還型、どちらを選択するかによって返済月額や返済期間は異なりますが、返済総額に変動はありません。
なお、所得連動返還型奨学金制度の対象者は、機関保証制度を選択している第1種奨学金の採用者です。
返済月額は「所得×9%÷12」で算出され、その額が2,000円以下になる場合、返済額は月額2,000円となります。
返済初年度は所得が確定していないため、返済開始から9月までの期間は定額返還型における割賦額の半額が返済額です。もし半額の返済が困難な場合は、申請により2,000円まで返済額を抑えることができます。この制度を利用しても月々最低でも2,000円の返済が必要となりますのでご注意ください。
返済月額は毎年10月に見直しが行われ、見直し後の返済額が適応されるのは同年10月から翌年9月までの1年間です。
所得連動返還型奨学金制度を利用するためにはマイナンバーの提出が必要となります。
その際の提出書類には「返還誓約書」「マイナンバー提出書」「番号確認書類及び身元確認書類(個人番号カード等のコピー)」があり、返還誓約書においてマイナンバーの利用に関する同意について署名・押印(奨学生が未成年の場合は親権者についても必要)を行います。
返還誓約書は学校へ提出し、マイナンバー提出書と番号確認書類及び身元確認書類(個人番号カード等のコピー)は日本学生支援機構が指定する宛先に直接提出しましょう。

奨学金受給Q&A
奨学金について、疑問に感じることも多いでしょう。よく聞かれる疑問についてお答えします。
- Q.審査は厳しい?
- 申し込む奨学金制度にもよりますが、申込資格や基準をすべて満たしていても、審査に通らないことがあります。特に日本学生支援機構の第一種や、第一種を第二種と併用して申し込む場合には、審査に通らない場合も。第二種は審査に通る可能性も高いため、併願する方がよいでしょう。
- Q.いつまでに申し込まなければならない?
- 多くの人が利用する日本学生支援機構の予約採用の場合には、高校3年の4月から7月頃までが申込期間となります。
- Q.いつから借りられる?
- 予約採用で申し込んだ場合には、専門学校入学後の4月から5月に貸与開始となり、月1回、振込によって貸与されます。また、専門学校入学後の在学採用の場合には4月分に遡って7月に貸与開始となります。
- Q.返済はいつからはじまる?
- 返済は貸与終了翌月から7ヶ月目に始まり、毎月27日に口座振替で支払います。また、前述のように月賦・半年賦の併用返還も可能です。繰り上げ返済は、いつでも手数料無料で行えます。
専門学校基礎講座【目次】
-
01
-
02
-
03
-
04
-
05
-
06
-
07
-
08
-
09