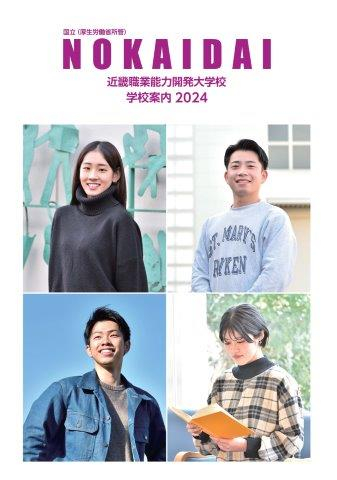建築・建設業界の今
人手不足が喫緊の課題。建築・建設業界に対策とは?
最高時から3割減! 建築・建設業界の就業人口
建築・建設業界は現在、人手不足が危機的な状態にあります。2020年の段階で就業者人口の36%が55歳以上に対し、30歳未満の就業者人口は1割程度。いわゆる2025年問題といわれる来年以降には高技能のベテラン層がごっそり抜けていき、産業の存続自体が危ぶまれる事態に突入します。
そこで、従来からの業界を取り巻く労働環境を抜本的に変革するような対策が急務となっており、具体的な改善策や各省庁や業界団体、各企業の間で取りまとめられています。それに基づき、若年層が魅力を持てる産業に向けて、急速に変化する可能性があります。
(参照:一般社団法人 日本建設業連合会/建設業デジタルハンドブック)

さらに業界に携わる人々の頭を悩ますのが、コロナ禍以後の公共事業の回復やインフラの改善への投資。2023年度は前年度比2.2%増の70兆3,200億円、2024年度は前年度比2.7%増の約73兆200億円となっており、今後も増加傾向にあります。このままでは、需要に供給が全く追いつかなくなります。
建築・建設業界が人手不足に陥る背景

人が足りないのは何が原因か?
これまでは下請け・孫請けの受発注が多く、現場で操業するのは「ひとり親方」が多い状況でした。つまり従業員数が極端に低い経営者がいくつもの受発注を通り、直接、現場で働いていたのです。また外国人の技能実習生によって当面の現場作業をしのいできましたが、これも為替の変動等により安定した雇用確保が難しい状況でした。さらに熟練の人材を育成するシステムも現代とマッチしないものとなり、受発注や工期管理のデジタル化や効率化も遅れていました。大手から発注→下請け・孫請け業者への発注でコストが上がる→各工程での効率化も阻害される→穴埋めの雇用に外国人技能実習生を採用するが、なかなか長期の技術伝承に繋がらず、労働環境の改善も難しい…という流れが大きな問題でした。
また、現代の若者の気質は「3K(きつい・汚い・危険)」の敬遠する傾向にあり、古いイメージの建築・建設業が、こうした産業の代表格と考えられてきたのです。
業界や省庁による変革の試みとは?
例えば、まずはどの業界でも取り組みが行われている「DX化」。建築・建設業の場合も、各工程における業務の進捗状況や図面・施工の状態が各施工者の間で共有できれば、業務が効率化でき労働時間も短縮できます。特に人力に頼る部分や個人の経験値で左右される部分を自動化・スマート化すれば、若者や女性の参入機会もアップします。
また、国土交通省も「建設キャリアアップシステム」を導入しています。これは、技能者の資格・社会保険加入状況、現場での就業履歴などを蓄積し、技能者の適正な評価や業務負担管理を行う仕組み。現在、外国人技能実習生に先行して導入されていましたが、これを全技能者に拡大します。どんな業務に習熟した技能者がどれだけ存在するかを、「見える化」します。
【その他の取り組み】
業界団体「一般社団法人 日本建設業連合会」ではこの他にも、人材確保や技能者育成についての提言を行っています。建設技能者の収入・賃金改善
優良技能者認定制度の設定などを行い、技能レベルに応じた賃金の適正化を図っていきます。
重層下請構造改善
下請けや孫請けでの受発注の非効率化を図るべく、丸投げの制限や下請けを三次以内とするなど、非効率な構造の是正を推進します。
社会保険未加入対策の推進
社会保険未加入者の排除を行うため、就労管理システムの構築を行い、元請けと直接雇用関係にない技能者の加入実態を把握します。
労働時間・労働環境の改善
作業現場の効率化を図り、工期に応じたスムーズな受発注を行うことで、労働時間の短縮や環境の快適化を達成します。
ほか
建築・建設業界の未来
自然災害などが多く国土も狭隘な我が国は、高度な建設技術の絶え間ないアップデートにより、高いレベルの建築を維持し続けなければなりません。そのためにも、「若手人材が魅力を感じる業界」を作り、技術の継承を適切に行うことが急務となっています。
それだけに、これからの業界のイメージや待遇が劇的に上昇する可能性を秘めています。自分が手掛けた仕事が形として残り、社会を動かすのがこの業界です。
時代とともに急激に変革していく産業に、自分の将来を託してみませんか?
東海工業専門学校金山校

近畿職業能力開発大学校