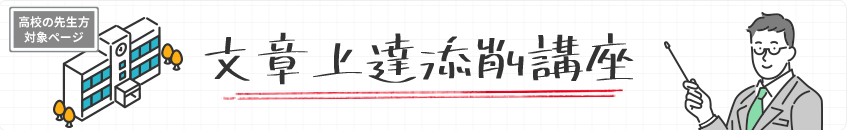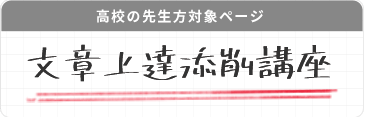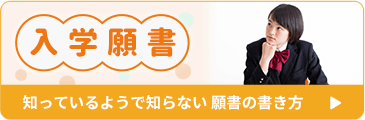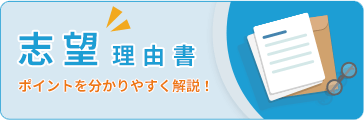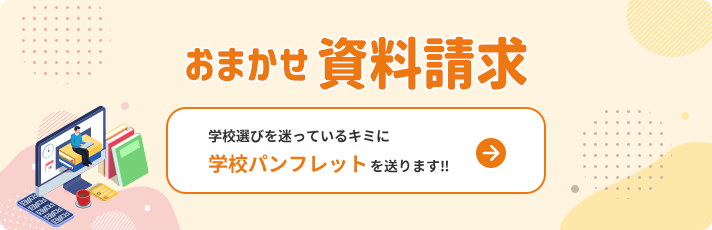STEP.3 小論文の段落構成・要約をマスターしよう
1. 段落の役割と内容
文章を読んでいると、改行で区切られた複数の文の塊があることに気付きます。この塊が段落です。
段落は、同じ意味や内容でまとめられています。つまり、1つの段落の中では、同じ話題についてのみ述べられています。このように、特定の意味や内容を分かりやすく示すことが段落の役割です。
ここでは、段落の構成の仕方として、「序論」「本論」「結論」という3段構成を紹介します。
| 段落 | 内容 | 分量の目安 |
|---|---|---|
| 序論 | 何について論じるかを定め(= 論点)、自身の考え(=主張)を明確に述べる。 | 10~15% |
| 本論 | 主張を裏付ける理由や具体的な事実(= 根拠)を説明する。 ※論点について述べる分量が多い場合などは本論で詳細に示しましょう。 ※本論を複数の話題で構成する場合は、段落を増やしても構いません。 |
65~80% |
| 結論 | 序論・本論で説明してきた主張をまとめる。 | 15~20% |
2. 形式段落と意味段落
ここで形式段落と意味段落について理解しておきましょう。
①形式段落
改行1字下げをしているところから、次の改行までのまとまりのこと。読みやすさを重視するために設ける。
②意味段落
意味や内容のまとまりによって分けられる。述べている内容が共通している1つ以上の形式段落で成り立つ。3段構成の場合、意味段落は3つ。
※3段構成の場合でも、形式段落の数は3つとは限りません。本論を2つの段落で構成する場合、形式段落は4つ、意味段落は3つになります。
3. 中心文(トピックセンテンス)
段落にはその中で最も述べたいことが書かれている文があります。その一文を中心文(トピックセンテンス)といいます。段落は意味や内容のまとまりごとに分けるので、1つの文に中心文は1つです。
以下の例文を参考に、各段落の役割と中心文の関係を確認しましょう。
- 序論:
- 若者言葉は、若い世代の会話やインターネットなどで頻繁に使われるが、乱れた言葉として否定的に捉えられることもある。若者言葉の特徴から、これらの言葉が否定的に捉えられる原因を考えたい。
- 本論1:
- まず、若者言葉の特徴として、娯楽のための言葉であることが挙げられる。例えば、「知らんけど」などは言い回しを楽しむために使われる傾向があったが、この点には会話を楽しむ効果が指摘できる。しかし、この効果は仲間内でのみ発揮される。相手や状況を選ばずに使われれば、意思を伝達するうえで違和感を生じやすい。
- 本論2:
- 意味が広いことも若者言葉の特徴である。例えば、「やばい」は多様な状態や感情を表現するよう変化した言葉であり、話者が言葉を選択する負担が少ない。しかし、このような言葉が多用されれば、詳細で的確な言葉を学び、使う経験は減ることになる。つまり、その使いやすさのために、話者が語彙を増やす機会を奪う可能性があるのである。
- 結論:
- 相手や状況によって違和感が生じやすいことや、話者が語彙を増やす機会を奪いかねないことは、若者言葉を使うことに伴う問題点である。 このような問題点を伴うことが、若者言葉が否定的に捉えられる原因であると考える。
4. 要約とは
要約とは、文章において筆者が述べたいこと、つまり要点を簡潔にまとめることです。課題文のある小論文試験の一部として出題されるだけでなく、それ全体が文章を読解するのに有効な手段です。その要約で役立つのが上記1~3で学んだ、各段落の役割や中心文に関する知識です。
5. 要約の手順
どのような課題文も基本的には以下の手順で要約します。
- ①まずは文章に目を通し、全体のテーマや段落の構成を把握します。
- <Point>
- 繰り返し登場する単語や表現があれば、キーワードとして印をつけておきましょう。
- ②段落ごとに、筆者の述べたいことを表した記述や中心文となる箇所を見つけます。これらが文章の要点です。
- ③文章の要点となる部分のみを抜き出し、具体例や体験談は省きます。
- ④指示語などに注意しながら抜き出した内容を書き出し、制限字数に合わせて文脈を整えます。
- <Point>
- 自分の考えや感想を交えず、筆者の主張をまとめましょう。
6. 要約の要領をつかもう
以下は、3. 中心文(トピックセンテンス)掲載の例文の要約です。要約は、中心文を基に組み立てられることが分かります。
- <Point>
-
- ⇒ テーマ 「若者言葉」が「否定的に捉えられる原因」
- ⇒ 段落構成 「序論」「本論」「結論」。3つの意味段落(4つの形式段落)で構成。
- ⇒ キーワード 「特徴」・「娯楽/楽しむ」・「相手や状況」・「意味の広さ」・「語彙」
- <例:要約>
- (序論)若者言葉の特徴から、これらの言葉が否定的に捉えられる原因を考えたい。(本論1)若者言葉には仲間内の会話を楽しむ効果はあるが、相手や状況を選ばずに使われれば、意思を伝達するうえで違和感を生じやすい。(本論2)また、意味が広く使いやすいため、話者が語彙を増やす機会を奪う可能性がある。(結論)このような問題点を伴うことが、若者言葉が否定的に捉えられる原因である。
目次
-
STEP.1
-
STEP.2
-
STEP.3
-
STEP.4
-
STEP.5
-
STEP.6