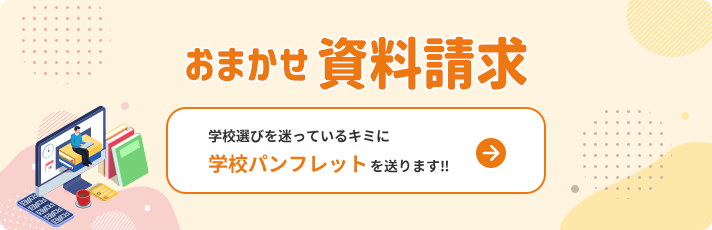在校生・先輩メッセージ
工学部 機械工学科
ずっと興味があった分野を学び、深めていく面白さ。
自分が好きな「ものづくり」で世の中に役立つ仕事がしたい。
ものごころついた時には工作に夢中で、中学生で機械の面白さにはまり、高校生の頃には材料へと興味が移っていきました。
埼工大を受験した理由は、まさに自分が学びたかった材料強度学の研究室があったから。材料の強度を上げるのは、人類が生まれてから何千年と続いている研究のひとつです。強化することで今までなかった設計ができたり、軽くて頑丈なものが世に進化をもたらします。
私の研究はまだ準備段階ですが、部品類の強度を計算するのは「ものづくり」の基盤を確かめている感じがして、とても楽しいです。
いま3年生ですが、2年生の学びと違う点は基礎から発展に進んだこと。いろいろな分野の基礎の組み合わせ、材料と物理を組み合わせるなど応用が増えましたね。
実は、埼工大を選んだ理由にはもうひとつあって、自転車競技を始めたかったからなんです。現在自転車競技部に所属していますが、選手としてもメカニック(整備士)としても本気。軽くて強い、そして速く走れるロードバイクの実現に、機械工学の専門性が活きていると実感しています。
将来は自分の好きな分野で世の中を動かす仕事がしたい。
「ものづくり」で社会貢献できれば嬉しいですね。

画像処理を使って、塗装の状態を判別。
機械× IT時代をこの手で感じています。
これを読んでいる工業高校生のなかで、大学では普通科目についていけないかもと心配している人も多いのでは? でも、埼工大なら大丈夫。
ここにいる僕が、証拠ですから。僕も同じような理由で大学進学をためらっていましたが、埼工大には学習支援センターや1年次に物理や数学の基礎を学べる体制が整っていることを知り、安心して進学。順調に大学生活を送っています。
現在ではほとんどの機械が、コンピュータ制御の時代ですよね。
だから、ITの知識や技術は大事。そんな僕が、いま研究室で取り組んでいるのが、二値化(にちか)という画像処理を活用して、塗装のキズなどを判別できるようにすること。
元の画像を白と黒に変換して見やすくするのですが、画像の二値化処理を行うには、白と黒に分けるための閾値(しきいち)という境界線を設定しなければならず、これがかなり難しい作業でして… 。設定によっては検知されない場合もあり、何度もトライして最適な値を追究しています。
そうそう、このまえ品質に関わる研究会で、この研究を発表する機会があったんです。
大学時代にそんな体験ができるなんて、まったく思っていなくて… 。
すごく緊張しましたが、最高の経験になりました。

ストレスの解消に効果的な「癒しの音」とは?
人のこころをサポートするロボット研究を進めています。
入学まで座学中心の授業をイメージしていましたが、この専攻は意外と手を動かし作業することが多いです。パソコンを使うのはもちろん、配線を繋いだり、溶接で火花が飛んだり。実際に機械の仕組みにふれるのは大切ですし、意外と楽しいですね。
4年間を通じて特に気にいっていたのは、レゴを使ってロボットを製作しプログラミングで動かす授業。初めての自作ロボットでもあり(失敗を含めて)印象に残っています。3次元のものを2次元に戻すCAD基礎製図の授業も、脳トレみたいで面白い。座学と実習が繰り返し行われるので、知識と技術がより身に付きやすいと思います。
私が所属するメカトロニクス研究室では、ヒトに寄り添う、より便利で安全なロボット開発を研究しています。ひとつ例を挙げると、装着することで麻痺した関節が動かせるリハビリ用の補助器具でしょうか。
現在は「ストレスの解消に、どの音が効果的なのか」をテーマに、卒業研究を進めています。心電図の数値をデータ化するのですが、ヒーリングミュージックや環境音、ASMRなどが、人をどのように癒すのか興味深いです。一見、研究室の分野とかけ離れているように感じますが、ロボットが人を助けるという意味で繋がっている。
心身の両面で、人を支えることができればと考えています。

工学部 生命環境化学科
世界初の青い花を咲かせたい。
そのカギは、遺伝子にあります。
あなたは、花に詳しいですか?では、エキナセアという花を知っていますか?
中心部の丸いふくらみがイガイガしていて、そのまわりに細長い花弁がついている花なんです。ハーブに利用されることもあり、花の色は、赤、ピンク、オレンジ、黄、白など、バラエティに富んでいます。
でも、なぜか青色の花だけは、いままで見つかっていません。不思議ですよね。
そこで研究室では、遺伝子組換え技術を活用して、世界初の青色のエキナセアづくりに挑戦しています。
まず無菌状態でエキナセアを育て、次にエキナセアの遺伝子のなかで、色素に関わっている箇所を探します。そして、その箇所を取り出し、
ほかの植物の青い色素に関わる遺伝子を導入すれば完成。…と、なるのですが、実際にやってみると、そんなに簡単な話ではありません。
無菌状態で育てるのはシビアで、色素に関わる遺伝子の特定においては試行錯誤の連続。それはそうですよね、簡単に“世界初”ができるわけがありません。
じつはこの研究は、先輩たちの代から引き継いだもの。少しでも青い花の誕生に近づけるよう、日々頑張っています。
ちなみに、エキナセアは埼工大に近い埼玉県寄居町の特産品。
寄居町のためにも、青いエキナセアの花を咲かせたい!

理想的な成分の開発から化粧品を見つめたい。
新たなスタートはいま、ここから。
理想の化粧品をつくりたくて応用化学専攻を選択しましたが、学ぶにつれ、既存の材料を組み合わせるよりも、成分そのものを開発したいという思いが強くなりました。
それほどまでに2年次からは専門知識や実験内容が深化しているのですが、とくに実験レベルが上がりましたね。なかでもレポート課題は、実験結果の考察に始まり、複数の参考文献を組み合わせて答えを導くもの、物理化学系など幅広い分野に関係するものもあり、時には仲間たちと「総力戦だ!」なんて言いながら、分からない点を教え合い、力を合わせて乗り切っています。興味深いのは、同じテーマでも生物系、化学系の授業でとらえ方が違うんです。立ち位置によって見方が変わる。物事は常に多面的で、それは生物や環境問題も重なることなので、視野を広げる必要性を感じています。
プライベートでは、いまドライブがマイブームなんです。友人に誘われて行ったドライブが本当に楽しくて。大学生活が180度変わりました。実は第一志望校の受験に失敗したことを引きずり、勉強とアルバイトに打ち込むことで、自分を誤魔化していた所があったんです。けれど綺麗な景色と開放感が、「学生の時にしかできないことがある」「未来はまだ決まっていない」と気づかせてくれた。
いま、毎日がとても新鮮で、かけがえのない時間の大切さをあらためて実感しています。

情報学 × 化学が生み出す便利さと付加価値。
多分野が協力し合い繋がることができる時代に。
埼工大では工学部内で同時受験が可能だと知り、情報系と現在の専攻を受験しました。
入学時点では自分の将来を決めかねていて、環境も面白そうだし、化学にも興味がある。もちろん情報系も…。そういった思いから、情報学も含め複合的に学べる現在の専攻を選びました。修得する中で、自分のやりたいことが明らかになっていくだろうという狙いですね。
所属する研究室はAIと化学の融合がテーマ。自分がかねてから研究したいと願っていた「情報学を取り入れた化学」が学べるのは嬉しいことです。私が情報学にこだわったのは、ITという共通の技術を利用することで、機械やバイオといった他分野が繋がり、互いに協力しやすくなる。それが当たり前の時代が来るという考えからです。
現在行っている研究は材料化学の分野で、再現実験の成功の兆しが見えています。こう書くとすごく順調そうですが、ミスから生まれた兆しなんですよね。研究当初は実験の意味を理解できず、失敗から学びを得ていなかったんです。大事なのはきちんとデータを取り、メモをし、ちょっとした変化の種も見逃さないこと。今は人の不便さを解消し、付加価値をつけることに魅力を感じています。
将来、そういったものを作ることができればと思案をめぐらせています。

工学部 情報システム学科
興味があったITの分野を初歩から学ぶ。
努力を重ねて好きなことを仕事にしたい。
ゲームやソフトウェアの仕組みに興味があり、設計や作る側に回りたいと考えていたんです。わりと目移りするタイプなので、情報系を学んでから専攻分野を選択するより、最初からプログラミングなどITに特化した学びをと考えていました。
とはいえ、入学時は高校の授業で習った程度の初心者レベル。キーボードの入力方法から授業が進むなど、不安なく学べたのは有難かったです。早くも1年次から、プログラミング言語でシステムを作る面白さを知りました。
2年次では仕組みについて学びます。たとえばなぜその動きをするのか、数式でどこに注目するか。基礎から深く掘り下げ、応用もできるようになった今、着実にスキルアップしている実感がありますね。
そのほかにも同時進行で行っているのが、資格取得のための勉強です。まずは基本情報技術者やITパスポートなどの資格を取得したい。その後、上位資格も狙えたら。学んできたことが形に残るって、いいと思いませんか?
将来は学びを活かせる仕事に就きたいです。好きなことを仕事にしたいんですよね。大手企業に就職した同専攻の卒業生の中には、入学時は私と同じ初心者だったという方もいる。大変な努力もされたと思いますが、1個ずつ積み重ねていけば目指す職に就ける、道は開けるという可能性を感じています。

アイデア次第で世の中が便利になるAI。
プログラムを操るために自分を磨いていく。
もともとパソコンを使って作業することが好きで、大学でも学びたいと考え進学しました。埼工大は就職率が高く、教職員のサポートも手厚い。学生生活を楽しむのは大事ですが未来も重要で、ここに安心感があると勉強に集中できますよね。
実際の授業は、1年次は基礎固めで、ここをベースに2年次の専門的な学びが本格化します。専門科目で面白かったのは、シューティングゲームをC言語で自作する授業ですね。C言語とは、ゲーム以外でも幅広く使えて応用がしやすい言語。この言語に慣れながらプログラミングをする中で、速さを変えたり、音楽を付けたり。なかにはイラストを取り入れた人もいましたね。基礎プラス知識という応用、個性で作品に大きな差が生まれたのは、とても勉強になりました( もっと頑張らないと! )。最近では対策講座の授業を中心に、基本情報技術者の資格取得の勉強にも力を入れてます。
そうそう、私は秋桜祭(学園祭)実行委員の活動もしていて、早くも2年目に入りました。時には他学科の先輩たちと夜中にラーメンを食べに出かけることもあり(笑)、大学生らしい、でも何気ない日々をとても楽しく過ごしています。
高校生の時はコロナ禍で思うようにいかなかった分、今とても充実していると感じています。

「自動運転」に関わってみたい!
その夢が、いま目の前に。
いきなり質問です。自動運転の研究に力を入れている大学って、日本にどれくらいあると思いますか?
大学進学のとき[自動運転 大学]で検索してみたんですが、9件ほどしか見つけられなくて。思ったより少ないんですよね。そして、そのなかでも、いろんな場所で実証実験の活動実績のある埼工大が目に止まり、進学することに決めました。
それまで埼玉のことはよく知りませんでしたが、自動運転を学ぶためなら佐賀から約1,000キロ、ここ埼玉へやって来ました!
そもそも僕が自動運転を学びたいと思ったのは、これからの時代はAI(人工知能)だと思い、そのなかでも自動運転に注目が集まっていたから。高校時代はパソコンにあまり触れて来ませんでしたが、大学での授業を通して着実に知識や技術を身につけ、いまではプログラミングもバッチリ。
そして、4年生になったら念願の渡部先生の研究室へ。渡部先生は、深谷市をはじめ西新宿や川崎など、全国各地で実証実験を実施中。いま僕は、研究室に入る前の肩慣らしとして、実証実験のときのデータ分析を行っています。本格的に研究に関わる日が待ちきれません。
そして、いつか自動運転で佐賀へ里帰りする日が楽しみです。

多彩な実験を通して実践的に学ぶ。
電気・電子分野のプロフェッショナルに。
冬はスノボ三昧、見てのとおり楽しいことが好きそうでしょ(笑)。
でも、こう見えて、しっかり将来のことも考えているんです。と言っても、まだ絞りきれてはいませんが、とにかく将来は電気・電子関連の技術者として働くつもり。
そのために埼工大に進学し、基本情報技術者や電気通信主任技術者などの資格取得にも積極的にチャレンジしています。これからの時代、ITやAIに目が行きがちですが、その基盤となっているのは電気や電子の世界。学んでみると、奥が深いんですよ。
とくに勉強になるのが、2年生から始まった週1回の「実験」。毎回テーマが変わり、それに合わせて専門分野の先生が担当。座学で学んだことを実験を通して実際に確認することができ、「なるほど!」と理解も深まります。
たとえば、一般家庭に普及している単相交流と、工場などで使用されている三相交流について、公式と照らし合わせながら電力や力率を実際に測定。電力を理解するうえで基本となる大切なことなので、とことんやりました。
ところで最後に…、次回の秋桜祭(学園祭)の委員長には、僕が就任。楽しいことが好きな僕にふさわしい、よりパワーアップしたものをお届けしますのでお楽しみに。

人間社会学部 情報社会学科
誰もが暮らしやすく働きやすい環境づくりへ。
「匂い」を通してアプローチしています。
匂いって、不思議ですよね。匂いによって、明るい気分になったり、嫌な気持ちになったり…。
いま研究室では、そんな「匂い」について研究しています。社会では、いろんな人が忙しそうに働いていますよね。そんな人たちに少しでもリラックスできる環境をつくるにはどうすればいいかを考えたとき、「匂い」がひらめきました。
でも、本音をいうと、少しだけ後悔しているんです。
研究をスタートさせ、匂いについていろいろ調べてみると、かなり手強いテーマで…。匂いは主観的なものなので人によって感じ方が違うし、空気にまじってしまうので数値化するのも難しいし。これからの研究プランとしては、対象をクルマの車内に限定して、匂いをパルス射出して、脳波でその反応を測定する予定。サンプルも数十人はほしいかな。どこまでできるかはわかりませんが、とにかく準備をスタート。
埼工大のいいところは、学生が「やりたい!」と思ったことを、先生がとことん応援してくれるところ。まさに“できる大学”!
このまえは、ほかの研究室の先生に頼んで『深谷市産業祭』に参加。飲み物を販売したり、ゲームのお手伝いをさせていただき、地域の方々と楽しいひとときを過ごすことができました。

現代社会で役立つIT技術はもちろん
自分が好きな音楽も学びたい。
メディア文化専攻*を知った時は「見つけた!」という気持ちでしたね。この専攻なら就職に役立つのはもちろん、自分の「好き」も満たせる。条件で決めた感じもありますが、実際に期待以上だと感じています。
専門科目で特に面白かったのは「ディジタルサウンド演習Ⅱ」。音楽制作ソフト「Logic」を使って作曲するのですが、自分のオリジナル曲でもいいですし、すでにある曲を耳コピして打ち込んでもいい。テーマも曲の長さも自由。
私にとって初めて音楽ソフトを使って1曲完成させることができた、思い入れのある授業です。大変だけど楽しかった。
3年生も後期になると、ゼミでの研究が始まります。論理的思考力を養い、それを伝えることが課題の大枠だと思うのですが、伝わるように話すって本当に難しい。人の数だけ視点や考え方があり、意見交換は自分にとっての新たな発見でもあり、成長にも繋がる大切な場。就活やこれからの人生を考えた時に絶対に必要なことなので、このゼミで鍛えていきたいです。
このメディア文化専攻は、IT、音楽、その他の分野といろいろなことが学べます。自分のどこを伸ばしたいのかも自由。「今、何がやりたいのか分からず悩んでいる」という人が入学しても、きっと将来を考えられると思います。
* 2025年4月 メディアデザイン専攻へ改称

人間社会学部・心理学科
過去の出来事から研究し、解き明かす。
心理学だからこそできる「救い」を学んでいきたい。
将来、警察官になりたい夢があり、犯罪心理学が学べる心理学を専攻しました。生活安全課などで、住民の心のケアやサポートができたらと考えています。
この授業は3年次で受けるのですが、犯罪を取り巻く事情が心理学の視点で捉えられ、とても勉強になります。現在は卒業研究の準備中で、題材は「その人自身のキャラクターと、その人の心理状態の相違についての研究」。
実は高校生の一時期、不登校気味になったことがあって。自分の弱音が吐けなかったんですよね。今思うとスクールカウンセリングを利用した方が楽だったのですが、周囲に「悩み? キャラじゃないよね」と思われたくなくて。心から頼れる友人を見つけたことで乗り越えられましたが、実際に経験したことを研究にと考えました。ただ、まだテーマが曖昧で。他のゼミ生からの指摘やプレゼンを聞くと「その発想、新鮮!」となって、新たな視点を模索したり組み込みたくなるんです。興味が膨らんで収拾がつかなくて、先生から「それはどうなるのかな?」と結論を求められることも(苦笑)。
でも、イチから企てるのは大好きなので、どのような心理学的技法を使うのか、質問手法を用いるのかを揃えていくだけで楽しい。
世の中に二つとない自分だけの論文を書くために、もっと視野を広げ、考え抜きたいと思っています。

心や行動の「なぜ」を知り未来の私に役立てたい。
大学生らしい「青春感」とともに。
「ビジネスに関する心理学を学び、これからの自分に役立てたい」。
そう思っていたので日常生活に関わる「消費者理解の心理学」の授業は、とても興味深かったです。消費者がどのような過程で行動を起こすのか。例えば店舗のレイアウトでは、色使いや照明など、商品の売り方にどのような心理学が応用されているのかを知ることができます。
これまでとは違った視点で、街や商品サイトを眺めるのは面白いですね。
今の時代はS N Sなどでつぶやきや評価を簡単に発信でき、良くも悪くも影響力があります。そこで卒業研究では、「マイナスな口コミの影響力」を題材に研究を進めています。たくさんの高評価やレビューがある中で、低・マイナス評価は購買意欲にどのような影響を及ぼすのか。HADという統計ソフトで数値を出すのですが、私にとって統計学は数学とは違って実に悩ましい。とにかく慣れるしかないと頑張っています。
これは高校生の皆さんへのアドバイスなのですが、大学では先輩後輩問わず、浅くでもいいので多くの人と関わりを持って欲しいです。深い友達も必要ですが、人と交流したぶん知恵や知識が自分の中に残っていきます。結果、自分も成長するし、論文などでも奥深いものができると思います。もうすぐ卒業ですが、その時々の瞬間、自分の好きなことを全力で楽しみたい。興味を持ったことにたくさん挑戦していきたいです。