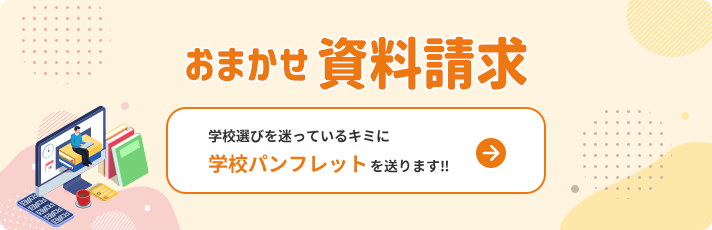自慢の先生・研究
工学部 機械工学科
上月 陽一 先生
材料を加工するとき内部で何が起きているのか? より良い製品をつくるための根本に迫っています!
材料強度学研究室
専門分野|結晶の塑性、転位論
たとえば鉄の棒にチカラを加えると曲がります。でも、よく考えてみる
と、なぜ曲がるのか不思議ですよね。材料を変形させたとき、材料の
内部ではどのような変化が起きているのか?元の形に戻らないのは、どのような作用が働いているのか?当研究室ではそれらを解明し、材料の強度との関連を調べています。一日一歩ずつでも前進・向上できるように、つねに笑顔で楽しみながら、一緒に研究に取り組みましょう。

河田 直樹 先生
知識や技術、そしてひらめきを総動員して、 「ものづくり」の現場をサポートしよう!
生産プロセス研究室
専門分野|計測制御工学、品質工学、交通機械
ものづくりのプロセスに関わることなら、ほとんどすべてが研究対象です。メーカーとの共同研究も積極的に進め、IoTを用いた鉄道車両の台車部品の状態監視技術の研究、AIを用いた色柄判別システムの研究、金属加工に関するIoTを用いた生産ライン監視技術の研究などでは実用化に成功。さらに、VRやAIを用いたメタバースの「ものづくり」に関する研究も行っています。あなたも「ものづくり」の工程に関わってみませんか。

萩原 隆明 先生
ロボットや機械を制御する方法を研究。 思い通りに動いたときの感動をその手に!
制御工学研究室
専門分野|制御工学、メカトロニクス
クルマや飛行機、工作機械などをコンピュータや電子機器を使って思い通りに動かすことが制御。当研究室では、幅広い対象の機械を制御するための研究に取り組んでいます。ひとつは理論研究で、数理的手法に基づいてモノをうまく動かすための方法を研究。もうひとつは、制御を用いたシステム機器やロボットなどの開発をめざしています。失敗を恐れず、失敗から学び、知識と経験を積み重ねて挑戦していきましょう。

工学部 生命環境化学科
石川 正英 先生
どんな遺伝子配列にすれば狙い通りの成果が得られるか? 興味深い遺伝子の世界を探索しよう!
遺伝子工学研究室
専門分野|遺伝子工学、分子生物学
「遺伝子組換え」というコトバを聞いたことがありますよね。遺伝子組換えとは、他の生物の遺伝子を組み込み新たな性質を持たせる技術。
当研究室では、医薬品のインスリンや洗剤に入っている酵素など、私たちの身のまわりで役立っているタンパク質を、遺伝子組換えによって大腸菌などの微生物を用いて大量に生産する技術開発を行っています。遺伝子に興味のある人は、この学科・専攻でとことん追究してください。

田中 睦生 先生
物質の本質を分子・原子レベルで理解。 いままでにない新しい材料をつくろう!
当研究室のモットーは、「生物に学び、物理で考え、化学で実現する!」。
イオンの種類を認識して分けることができる分子認識材料や、プラスチックなのに電気が流れる有機導電性材料など、物質の本質を分子・原子レベルで理解し、いままで世の中になかった新しい有機材料の開発に取り組んでいます。分子という目に見えない物質を扱うので、頭の中でイメージしながら、じっくり丁寧に研究を進めていきましょう。

松浦 宏昭 先生
これからの社会に喜ばれる技術開発を。 あなたの研究が新しい未来をつくるかもしれません!
環境計測化学研究室
専門分野|電気化学・分析化学・エネルギー材料化学
その手で、未来にアプローチしてみませんか。社会が求めている技術を考え、その研究開発に取り組んでいます。たとえば、クリーンエネルギーの未来を支える長寿命なレドックスフロー電池の研究や、環境にやさしい水素エネルギーを安価に生産する研究などを行っています。企業連携により、実際に実用化されたものもあります。自分の研究が、これからの未来づくりに活かされるかもしれない醍醐味を、ぜひ味わってください。

工学部 情報システム学科
鯨井 政祐 先生
AR・VRを使って、ヒトはもっとつながれる。 未来の面白いアイデアをカタチにしよう!
ヒューマンインタフェース研究室
専門分野|ヒューマンインタフェース、ヒューマンコンピュータインタラクション
AR技術・VR技術などを使いながら、ヒトとヒト、ヒトとモノをどうつなげるかの研究・開発を行っています。たとえば卒研テーマのひとつとして取り組んだのが「TeleContact」。これはスマホ画面を通じてお互いを「触ることができる」テレコミュニケーションシステムで、学内研究フォーラムで最優秀ポスター発表賞を受賞しました。SF映画に出てくるようなワクワクする未来の道具を、一緒につくりましょう。

望月 義彦 先生
AIによる“目”は、どこまでヒトを超えられるか。 さまざまなシーンでの活用を研究しています!
視覚情報処理研究室
専門分野|コンピュータビジョン、ロボットビジョン、画像処理、人工知能
現在、私たちヒトは、コンピュータによる新しい「視覚」を手に入れました。当研究室の主なテーマは、AI(人工知能)を活用したカメラ画像の認識。たとえば、人の体や手のポーズの認識を利用した技術では、楽器の採譜や演奏を評価するものや、ゲームの操作法を考える研究などをしています。さらに、全方位画像などからの情報を数理的・幾何的に解析・理解し、ロボットナビゲーションなどへの応用もめざしています。

渡部 大志 先生
自動運転があたりまえの未来へ向けて。 その日が来たとき、中心で活躍しよう!
自動運転AI研究室
専門分野|自動運転
現在、深谷市をはじめ、西新宿や川崎など各地で実証実験を行い自動運転バスを走らせています。研究室には自動運転に関わる企業エリートや国内トップレベルのエンジニアが出入りしていて、自動運転の最前線に日頃から見て触れる機会があります。自分が関わった箇所が、実証実験で動くかドキドキするのも楽しい経験です。そして、自分が関わったものが実際に走っているのを見て、ぜひ感動してください。

藤田 和広 先生
コンピュータを使って電磁気の世界に迫る。 電磁気学のスペシャリストをめざそう!
計算電磁気学研究室
専門分野|電磁場解析、環境電磁工学、加速器工学
近年、電気電子工学の世界でも、AI(人工知能)を活用する技術が急速に進んでいます。当研究室では、ビッグデータを使わずに電磁気の現象や電気回路の特性を人工知能に学習させる技術と、それをプリント回路基板、導波管などの設計に応用する研究に力を入れています。
深層学習などの人工知能技術をエレクトロニクス分野で応用する経験を通して、次世代のものづくりを支える人材をめざしてください。

人間社会学部 情報社会学科
村山 要司 先生
AIなどの技術を、経営戦略に活かす。 経営と情報に精通するスペシャリストに!
経営情報研究室
専門分野|経営情報、コンピュータサイエンス
さまざまな経営問題に対して、データマーケティング、AI(人工知能)、数理最適化といったコンピュータサイエンスを活用して、マーケティング分析やビジネスプロセスの効率化を図る研究を行っています。近年、ITが経営に及ぼす影響が大きくなり、経営戦略と情報戦略を同時に考え、推進していくことのできる人材が求められています。ここでの研究を通して、社会人として活躍できるスキルを身につけてください。

森沢 幸博 先生
情報技術が生み出す可能性を信じて、 コミュニケーションの未来をデザインしよう!
メディアデザイン研究室
専門分野|CG・メディアデザイン
コンピュータを道具として自在に使いこなすことで、私たちがいままでできなかったコトやモノを創り出すことができるようになりました。I CT(情報技術)は人間の表現能力や社会の仕組みを刷新する力を持っています。当研究室では、CG動画やデジタルコンテンツ制作、現実感を拡張する最新技術を利用した表現の可能性について追究。キャラクターデザインや映像制作を通じて、創造(想像)する楽しさと喜びを一緒に体験しましょう。
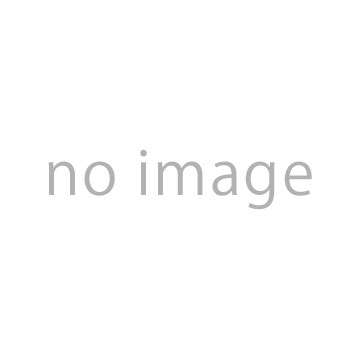
人間社会学部 心理学科
滝澤 毅矢 先生
こころの健康について幅広く研究。 人のこころに寄り添える対応力を身につけよう!
臨床心理学研究室
専門分野|臨床心理学、医療心理学、精神医学、心理アセスメント
医療的なこころの支援や心理検査を使った人間の理解について研究しています。とくに認知症のある方や介護職の方、精神疾患に悩む方や死にたい気持ちを抱える方、子育てに悩んでいる方など、広い年代を対象としたこころの健康に関する実践的な研究を展開しています。
臨床心理学は「人を支える」ということを大切にしている心理学の一分野です。人のこころを支援する方法について一緒に考えていきましょう。

河原 哲雄 先生
どのようにしてコトバや知識を覚えるのか? 情報処理の観点から「心」を見つめます!
基礎心理学研究室
専門分野|認知心理学・言語心理学
ヒトはどのようにして、学習や経験を通じて、コトバや知識を使えるようになるのでしょうか? また、ヒトの記憶の仕組みはどうなっているのでしょうか? 当研究室では、その課題に対して、心理学実験や情報処理モデルの手法を用いて研究しています。さらに、消費者行動に関わるテーマや、顔の魅力のような対人認知に関わるテーマなども展開。複雑だけど面白いヒトの心の働きや仕組みを、一緒に覗いてみませんか。

学生活動
がんばる!学生プロジェクト
Hondaエコマイレッジチャレンジプロジェクト
1Lのガソリンでどれだけ走れるか。燃費を競う競技車両の製作
本活動はホンダエコマイレッジチャレンジの競技規則に則った車両を製作し、10月に行われるもてぎ大会に参加、及び完走を目標とし活動を行う。
大会の内容として、カブ用50CCエンジンを使用した車両にドライバー1人を乗せて走らせ、燃費を競う競技である。また、車を製作する過程で、実践的な3DCADや工作機械の使い方、4大力学を学ぶ。

SAIKO Aquarium Project
メダカをはじめとした様々な水生生物の飼育・展示
昨今の日本では野生の生物に対して学ぶ機会が少ない。数多くの日本固有の水生生物が絶滅の危機に瀕しているという現状を、多くの人に広めるため活動する。本学の学生や教職員をはじめ、来客や地域の方々へ、様々な水生生物に興味、関心を持つ場を提供する。日本人の野生生物に対する意識を変える。

米と日本酒(米作り、そして日本酒へ)プロジェクト
埼玉工業大学オリジナルの日本酒を醸造する
農家の方と共同で埼玉のブランド米である「彩のかがやき」を使用し、苗を植えるところから稲刈りまで行う。そしてその米を使用し深谷の酒造会社・丸山酒造さんのご協力を得て、日本酒造りを行う。さらに、酒造会社さんと共同で、埼玉工業大学オリジナルの日本酒ブランド「瞬喜道」を商品化し、地域のイベントを中心に販売し、本校を知ってもらうとともに、地域の方々と交流する。

ロボット研究プロジェクト
2足歩行ロボット格闘大会への出場
ロボットを製作し、改造やプログラミングを行い、ROBO-ONE Light優勝を目指す。さらに、学外の技術者の方々との交流会を開催し、練習試合や意見交換を行うことで、操縦技術を向上させ、ロボットに関する技術や知識を習得する。他にも、認定大会や地方の大会に参加することで、実戦経験を積む。それ以外にも、催事やイベントに参加し、ロボットの操作体験を行うことで、ロボットの魅力や楽しさを一般の方に伝える。

SAIKO謎解きプロジェクト
謎解きを通じて「分析力」「企画力」を向上させる
謎解きに興味を持ち、日常を注意深く見る「観察力」、新しいものを作り出す「創造力」、アイデアを出力する「表現力」、個人の意見を尊重して仲間と協力する「協力性」を目的とする。