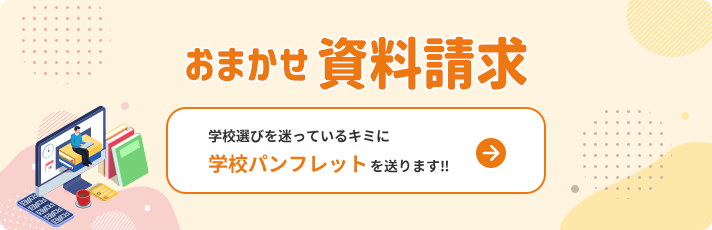学部・学科・コース
経済学部
学べること
経済学は、お金やモノの流れを分析して社会課題の解決を目指す学問です。国家や産業、企業、消費者について研究し、マクロ(巨視)とミクロ(微視)それぞれの視点から社会の動きを捉えます。本学の経済学部では、実践的な学びを重視し、フィールドワークやデータサイエンスプログラム、英語との連携科目や独自の留学プログラムなどを展開しています。自ら動いて経済を肌で感じることで、実社会で役立つ問題解決能力を身に付けます。「現代経済」「ビジネス経済」「地域経済」「グローバル経済」の4コースを設置しています。
学科・コース

経済学科(現代経済コース、ビジネス経済コース、地域経済コース、グローバル経済コース)
「現代経済コース」
少子高齢化、社会保障、地球温暖化など、現代社会が抱える諸問題の原因や解決策を、経済学の視点から考えていきます。また、行政が市場に果たす役割や課題、財政への影響についても考察します。
「ビジネス経済コース」
経済環境の変化が産業構造に与える影響をビジネスの視点で分析。企業活動や経済政策の事例から、日本の産業構造についての理解を深め、企業戦略を構想できる力を身に付けます。
「地域経済コース」
地域社会が直面する課題の解決方法を多様な視点から考察。自治体・企業・住民それぞれの立場から見た、豊かな地域経済・社会の在り方を探ります。
「グローバル経済コース」
貿易や金融など、国際取引に関する問題をグローバルな視点で分析。経済メカニズムを明らかにし、国際経済問題を解決に導く道を探りながら、「世界の中の日本経済」の動向を考えます。
経営学部
学べること
経営学は「組織」の維持発展について考える学問です。本学の経営学部では、ケース分析をはじめ、企業やスポーツチームの課題解決に取り組むなど実践的な学びを重視し、経営者やマネージャーに必須の思考力・分析力・企画力を養います。近年はデジタル・トランスフォーメーション(DX)関連科目で最先端技術とマネジメントを融合する学びを展開し、イノベーション人材の育成に注力。公認会計士などの資格取得をサポートする環境も整えています。
学科・コース

マネジメント学科
経営学部では、3つのドメイン(知識領域)から横断的に科目を選んでいくシステムを採用。3年次に3つのドメインのうち1つを「リーディング・ドメイン」として学びの主軸に定め、さらに残り2つのドメインの科目も組み合わせて学ぶことで、それぞれの分野と関連する体系的な専門知識と学際的な知識を修得します。
【Strategy & Organization(戦略と組織)】社会や企業経営において重要なファクターとなる組織について学びます。併せて組織運営に関連する経営戦略を学修し、競争優位を実現する知識を身に付けます。
【Marketing & Innovation(マーケティングとイノベーション)】消費者行動の分析や市場ニーズに応える製品・サービスづくりに必要な市場調査や流通、販売などについて学びます。革新的な製品・サービスを実現するノウハウも修得します。
【Accountability & Governance(アカウンタビリティとガバナンス)】企業をはじめとする組織が社会的責任(CSR)を果たすための適正な資金運用や会計知識を体系的に学びます。また社会貢献や環境への配慮なども学修します。
法学部
学べること
法学部で学ぶのは、法律や政治、政策など、社会を支える「しくみ」と「はたらき」です。本学の法学部では、現場に足を運び活発な議論を行うアクティブ・ラーニング科目、先輩と後輩が共に学ぶ科目など、学部独自の取り組みを多彩に展開。このような学びで身に付く「社会のルールを熟知し、正しく議論する力」は、社会のインフラを支える人にとって必要不可欠な素養。4年間の学びを通じて、人や社会を守るための論理的思考力、実践力を育成します。
学科・コース

法律学科(法律総合コース、社会安全コース、政治・国際コース)
1年次に導入科目でベースとなる知識を修得。2年次からは、社会における法の働きを専門的に理解し、社会人に必要な法的判断力を養う「法律総合コース」、警察官や消防士などを志望する人に適した「社会安全コース」、国内外の複雑な問題を解決に導く「政治・国際コース」の3コースに分属し、将来の進路を見据えた、より専門的かつ実践的な学びを深めます。

法政策学科(地域公共コース)
法政策学科では、国や地方の社会的公共性をしっかりと理解し、さまざまな分野で社会を法的・政策的に支えていきたい人が対象の「地域公共コース」を設置。国家公務員、地方公務員、NPO職員、あるいは地域住民として、法を踏まえて政策を企画する能力を得ることを目標としています。さらに、政策に関する基礎知識を理解し、グループ学習によって調査・分析する力、対策案をデザインする力、コミュニケーションを取る力を修得する「法政策基礎リサーチ」も実施しています。
現代社会学部
学べること
社会学とは社会に潜む課題を見いだし、解決に導くための学問です。人とのつながり、地域の在り方、メディアの未来など、広範な「社会」に対し、経済、法律からスポーツ科学まで、あらゆる学びを結集して挑みます。特に現代社会の課題は高度に複雑化しており、人との協働がなければ解決には至りません。そこで、現代社会学部では「次世代型リーダーシップ」の養成を掲げ、人をむすぶ素養を身に付ける科目から、実践の場に立つ演習科目までを多彩に展開。独自のカリキュラムで次世代型リーダーを育成します。
学科・コース

現代社会学科
社会学の基礎知識と調査手法を取得し、自分の関心に合わせ、専門科目を幅広く学びます。さらに「地域社会学」「人間社会学」「メディア社会学」にかかる諸問題解決のために多様な専門知識を深めます。2年次以降、各自の関心や将来の進路に合わせて選べる4つの履修プログラムで専門性を高めていきます。
◆地域社会学プログラム
国内外の地域の特色を学ぶだけでなく、地域社会で起きている社会現象や社会構造を多面的に理解し、地域の課題解決策や多文化共生などについて考える科目が配置されています。
◆人間社会学プログラム
家族・ジェンダー・教育・心理・労働などの幅広い視点で、現代社会における人と人との多様な関係性と新しい可能性にアプローチすることができる科目が配置されています。
◆メディア社会学プログラム
テレビ・広告・マンガ・インターネットなど、人や社会を動かす力を持つメディアの変わらない本質と、変わりゆく方向性を見極めたり、情報発信や表現の方法を学べる科目が配置されています。
◆データ社会学プログラム*
ビッグデータやAIなど、私たちの身近にも「データ」があふれていますが、社会学においてもデータを駆使して社会を理解する必要性が高まってきました。そこで新たに「データ社会学プログラム*」を設置します(地域社会学・人間社会学・メディア社会学の各プログラムと並行して登録可)。単に「データを扱う」だけでなく、人間の感性を生かして「データから社会を読み取る」力の修得をめざします。
*2026年4月開設予定/内容は予定であり、変更が生じる場合があります。

健康スポーツ社会学科
健康・スポーツを科学的に追究するための高度な実験・実習設備が充実した環境で、さまざまな角度からデータの収集・解析を行います。「社会学」と「健康・スポーツ科学」を融合し、新しい視点で健康・スポーツの可能性と価値を探究。高度な専門性を身につけ、健康で活力ある社会を築く力を育成します。
◆スポーツ・データサイエンス・プログラム*
スポーツ現場でのデータ分析や活用が可能となる人材育成をめざした教育プログラムを開始します。このプログラムでは、「スポーツデータ解析論」「スポーツ映像解析論」などの履修を通して専門的な知識や技術を深めていきます。
*2026年4月開設予定/内容は予定であり、変更が生じる場合があります。
国際関係学部
学べること
本学の国際関係学部では、世界を動かす人材に不可欠な「実行力」を育み、「専門性」を養います。1年次の必修科目「海外フィールド・リサーチ」と、学内での活発な「リサーチ・議論」を学びの柱とし、政治・経済・共生などの学術的視点から、広範で複雑な国際問題に挑戦します。英語でも日本語でも情報を収集・議論・発表できる学びを通して、国際社会での活躍に必要な専門知識と英語力を同時に身に付け、論理的思考力と情報分析力を駆使し「国際社会の発展と平和に寄与できるグローバル人材」を育成します。
学科・コース

国際関係学科(国際関係・政治コース、国際関係・経済コース、国際関係・共生コース)
国家間の課題を発見し、その解決に取り組むのに必要な知識や分析力を獲得する「国際関係・政治コース」、グローバル経済と国内産業構造の変化を総合的に捉え、日本経済の発展を考察する「国際関係・経済コース」、国際社会の問題をさまざまな視点から分析し、共生の観点から解決策を探る「国際関係・共生コース」の3コースに2年次から分属。各領域の専門知識を段階的かつ体系的に修得するとともに、国際関係分野の学際的な科目を学修します。また、国際関係学の専門知識を深め、情報を分析し解決力を身に付ける参加型・双方向型授業(アクティブ・ラーニング)を中心に展開。少人数クラスでグループワークやディスカッションなど学生自身による主体的な学びを展開します。講義形式の科目でも民間企業や公的機関から招く外部講師による授業などを行い、トータルに実践力を養います。
外国語学部
学べること
本学の外国語学部では、私立大学屈指の10言語が学べる3学科12専攻を設置。各言語を体系的に学べるカリキュラムを展開しています。学びの基盤となる専攻語の授業では、「話す」「聞く」「書く」「読む」の基本4技能はもちろん、ディベートやプレゼンテーションを通し、幅広い視野や高い表現力を身に付けます。また教養面では、全専攻において各国の文化・歴史を探究し、世界に通用する豊かな教養を修得。加えて、学生が積極的に学ぶアクティブ・ラーニング型授業や留学を通して、異文化間コミュニケーション能力や問題解決力を身に付け、国内外で活躍するグローバル人材を育成します。
学科・コース

英語学科(英語専攻、イングリッシュ・キャリア専攻)
グローバル社会で活躍できる英語力の獲得をめざす「英語専攻」、翻訳・通訳やエアラインといった国際的なサービス業など、専門職として英語を扱うための高い語学力と専門知識を養成する「イングリッシュ・キャリア専攻」の2専攻を設置。英語によるレベル別のきめ細かい指導が行われる授業や充実した留学体験を通して、国際社会で役立つ高いコミュニケーション能力を築きます。

ヨーロッパ言語学科(ドイツ語専攻、フランス語専攻、スペイン語専攻、イタリア語専攻、ロシア語専攻、メディア・コミュニケーション専攻)
「ドイツ語」「フランス語」「スペイン語」「イタリア語」「ロシア語」の各専攻と、メディアを使って世界に表現する力を養成する「メディア・コミュニケーション専攻」の6専攻を設置。各国の言語だけでなく、歴史や文化、思想、経済、メディア技術などについても横断的に学ぶことで、その多様性に触れていきます。

アジア言語学科(中国語専攻、韓国語専攻、インドネシア語専攻、日本語・コミュニケーション専攻)
アジア圏の言語を専門的に学ぶ「中国語専攻」「韓国語専攻」「インドネシア語専攻」と、日本語教師や中学校・高等学校の国語科教員になるための実践力を磨く「日本語・コミュニケーション専攻」の4専攻を設置。今や世界経済のけん引役となったアジア。その歴史や文化、政治、経済などを幅広く学ぶことで、多様な分野でグローバルに活躍する人材を育成します。
文化学部
学べること
2026年4月、文化学部は伝統的な人文学を基調としつつ、次世代を見据えた新たな研究領域を切りひらき、実社会に対して学びの成果を提供・還元・発信していくために、文化構想学科、京都文化学科、文化観光学科の3学科体制へと生まれ変わります。
生成AIやデータサイエンスを活用したデジタルヒューマニティーズを展開する人材の育成を目指し、人文学の学びを進化させます。また、京都や日本、世界の文化フィールドでの学びを通じて文化理解力を高め、京都を学びの場・対象とする独自の教育を提供します。さらに、英語特別コースや長期留学を通じて実践的な英語運用能力を強化し、国際社会で文化問題に主体的に取り組むグローバルな人材を育成します。
学科・コース

文化構想学科*
1年次では、演習科目「入門セミナー」で文化構想学を学ぶ基本を修得。講義科目「文化構想学概論」で異文化理解の思考と多様性、国際性の基礎を学びます。2年次からは、「基礎演習」で研究手法を身に付け、個人の興味関心に応じて、学びの領域(文化表現/文化理解/文化情報・交流)に基づく科目を自由に選択。英語特別コースに所属し、良質な英語運用能力も身に付けることができます。3・4年次では、「演習I・II」で本格的な研究を行い、4年次には卒業研究に挑戦。一人一人の興味や関心をもとに研究テーマを深掘りします。

京都文化学科
1年次では、演習科目「京都文化フィールド演習」で京都文化を五感で感じ、講義科目「京都文化学概論」で京都文化学の基礎を身に付けます。2年次からは、「基礎演習」で研究手法を身に付け、個人の興味関心に応じて学びの領域(歴史文化/文化遺産/文化情報・交流)に基づく科目を自由に選択。英語特別コースに所属し、良質な英語運用能力も身に付けることができます。3・4年次では、「演習I・II」で各自の研究テーマに取り組み、日本文化・京都文化へのより深い理解を目指します。その集大成として4年次には卒業論文を作成します。

文化観光学科*
1年次では、演習科目「観光調査演習」で調査・研究の実践的方法を学び、講義科目「文化観光学概論」で文化観光学やデジタル分野の基礎を学びます。2年次からは、「基礎演習」で研究の基盤となる力を身に付け、個人の興味関心に応じて、学びの領域(観光文化/地域づくり/観光産業)に基づく科目を自由に選択。英語特別コースに所属し、良質な英語運用能力を身に付けることもできます。3年次では、「演習I」から、本格的に研究がスタート。課題解決型のPBLやインターンシップなど、多数の実践的な学びにも取り組み、その成果を生かして4年次には卒業研究を完成させます。
*2026年4月開設予定、仮称・設置構想中。学部・学科名等、掲載内容は変更になる場合があります。
理学部
学べること
数学・物理学は、自然科学の根源を学ぶ万人のための基礎学問です。理学部では少人数体制のクラス編成や、体系化されたカリキュラムを設置し、数学や物理学に向き合える環境を整えています。教職やエンジニア、金融などのビジネス領域まで、さまざまな進路につながる科目を展開。さらに、高度なデータサイエンススキル修得のための科目を必修化。全ての学科において、理系人材が修得すべき「数理・データサイエンス・AI教育プログラム(応用基礎レベル)」を必ず身に付けて卒業できる文部科学省認定カリキュラムを提供しています。Society5.0社会を根幹から支え、新たな価値をうみだすことができる人材を育成します。
学科・コース

数理科学科
マーケティングやWebの検索エンジン、感染症流行予測など社会で幅広く使われている数理科学を、代数学系、幾何学系、解析学系、応用数学系の4分野を組み合わせて体系的に学修。ビジネスをはじめ、さまざまな分野に応用の利く“生きた数学”を身に付けます。教員志望者のための「数学教育コース」、ビジネス界を視野に入れた「BizMath(ビズマス)コース」を選択可能です。

物理科学科
実験や演習を交えながら、力学や熱力学、電磁気学といった基礎を修得した上で、量子力学や相対性理論、物性物理などの専門分野へと学び進めます。「スペシャリスト支援プログラム」では、理論と実験の専門家として活躍する人材を育てます。また、宇宙産業のものづくり人材育成のための「宇宙産業コース」と、半導体物理を学べる「半導体産業コース」を設置。興味や進路に応じて選択できます。

宇宙物理・気象学科
物理学の基礎を身に付けるとともに、地球大気から宇宙空間へ至るスケールの大きな物理現象を総合的に学修。国内私立大学最大口径の望遠鏡や最新の観測装置を使用した専門性の高い実習を交えながら、宇宙の謎や地球・惑星を取り巻く諸問題の解明に挑みます。海外の研究機関やJAXA(宇宙航空研究開発機構)などの世界の研究者とも連携しています。
情報理工学部
学べること
世の中のあらゆる「こと」をデータ化することで、人類は高速で精密な分析やサービスを行う力を手にしました。本学の情報理工学部では、そんな「情報科学」を駆使するための理論と実践を学びます。カリキュラムでは専門領域を10コースに体系化し、組み合わせることで新たな分野に対して創造・挑戦しやすい環境を整備しています。さらにファブスペースや実験住宅といった最新機器・設備を積極的に活用することで、情報科学を扱うプロフェッショナルを育成します。
学科・コース

情報理工学科(ネットワークシステムコース、情報セキュリティコース、データサイエンスコース、ロボットインタラクションコース、コンピュータ基盤設計コース、組込みシステムコース、デジタルファブリケーションコース、脳科学コース、メディア処理技術コース、情報システムコース)
情報理工学部では、1年次の秋学期にコースを選択します(最大3つまで)。その上で、各分野・領域の専門知識を身に付ける要件科目と、より幅広く学ぶための補強となる推奨科目を通して、段階的に学びを深めていきます。
「ネットワークシステムコース」
サーバコンピュータからネットワーク、クラウド環境に至るまで、ITシステムや通信の設計・開発・運用など、ITインフラを支える技術を身に付け、進化し続けるネット社会を支えるエンジニアを目指します。
「情報セキュリティコース」
Webサービスを利用するためのインターネット通信から大規模な産業システムの運用管理まで、幅広い分野でニーズのある、情報漏えいの防止やウイルス対策をはじめとしたセキュリティ技術を学びます。
「データサイエンスコース」
新たなビジネス発掘や問題点の発見につながるビッグデータ解析技術や機械学習技術を中心に学修。ビジネスとITどちらの世界にも精通した、人工知能技術者やデータサイエンティストを目指します。
「ロボットインタラクションコース」
蓄積されたデータを利用し、受付ロボ、商品配達ドローン、自動運転車などのロボットを制御する技術を学び、ロボットと人の協調作業を創出。サービスシステムの設計やカスタマイズにも挑みます。
「コンピュータ基盤設計コース」
情報科学と情報工学をベースに、ハードウェアやソフトウェア、ネットワークの基盤技術、設計を含めた実践的技術を修得。情報化社会で時代が求めるビジネスインフラを作る人材を目指します。
「組込みシステムコース」
インターネットに接続された家電などのIoT機器やスマートウォッチなどのウェアラブル機器。これらに使用されるハードウェア・ソフトウェア技術を中心に、回路設計や機器・ソフトウェア開発などの技術を学びます。
「デジタルファブリケーションコース」
3Dプリンタなどの機材を活用し、ウェアラブル機器を作るなどの体験を通じて、ファブ社会(デジタル技術を用いてさまざまな人がつながる新しいものづくり社会の仕組み)をけん引する力を養います。
「脳科学コース」
脳や身体の働きを学んで、生物の情報処理の仕組みなどを理解。脳の働きと連携させた福祉機器や医療機器、IoT機器など、最先端機器開発へつながる発想力と技術力を身に付けます。
「メディア処理技術コース」
ゲームやSNSなどの音声や画像といった情報メディア処理の基礎技術やVR、ARの応用技術を学びます。ゲームの世界だけでなく、医療現場や建設現場など、ビジネスでの活用を目指します。
「情報システムコース」
情報システム、人工知能、ITインフラといった幅広い情報技術を修得。ビジネスに直結した戦略的な業務システムの設計・開発・運用を行う、次世代のシステムエンジニアを目指します。
生命科学部
学べること
本学の生命科学部では社会の諸問題を「健康・医療」「食料・資源」「環境・生態」の3領域に集約。実験科学を中心とする「先端生命科学科」と、社会科学を取り入れた「産業生命科学科」の2つの異なるアプローチから探究します。従来の学問分野での縦割り教育ではなく、生命科学を社会との接点から見つめ直し幅広く学ぶことで、課題を解決し、さらなる社会の発展に貢献できる人材を育成します。また、本学部では他大学に例を見ない、教員1人に対し学生約5人という少人数教育を実現しています。実験系の学部で不可欠な少人数教育の徹底により、質の高いきめ細かな指導で教員が学生と常に向き合う体制を整えています。
学科・コース

先端生命科学科(生命医科学コース、食料資源学コース、環境・生態学コース)
1年次では生命科学の基礎を修得。2年次からは、ヒトや動物の医療・健康に貢献できる専門性を養う「生命医科学コース」、生命科学の手法で食料問題などの解決方法を探究する「食料資源学コース」、生命科学をマクロに捉え、生命と環境に関わる「環境・生態学コース」の3コースに分属し、専門分野の学びを深めます。さらに、3年次秋学期からは指導教員の研究室で自ら設定した課題に挑む研究活動へ。十分な学識と実績を持つ教員の指導の下、高い専門知識と技術、倫理観を兼ね備えた人材を育成します。

産業生命科学科(医療と健康コース、食と農コース、環境と社会コース)
1年次では生命科学の基礎となる科目を履修。2年次からは、医薬系・生命科学の研究成果と、医療や医薬品関連産業との結び付きを学ぶ「医療と健康コース」、農業に関連する動植物を対象とした生命科学の研究成果と、社会の関わりを探究する「食と農コース」、里山生態学などの学びを通して、地域を取り巻く環境問題を理解・発見し、その解決策を考察する「環境と社会コース」の3コースに分属し、専門分野の学びを深めます。3年次からは「生命科学インターンシップ」や研究活動などで課題解決に挑戦。社会との連携を重視した教育プログラムを通じて、生命科学と社会をむすび、研究成果を実社会で活用できる人材を育成します。
アントレプレナーシップ学環*
学べること
アントレプレナーシップとは、新しいアイデアで変革を起こす行動力と挑戦するマインドを指します。AIが進化する現代では、起業家に限らず、柔軟な思考力や問題解決力、他者との協働力を備えた人材が求められています。こうした能力を育むため、一拠点総合大学の特長を生かし、経営・法・現代社会学部を横断する新しい教育形態「学部等連係課程」として、「アントレプレナーシップ学環」の開設を予定しています。この学環では、アントレプレナーシップやビジネス創造に必要な専門知識を幅広く学び、学士(ビジネス)が授与されます。
本学の「アントレプレナーシップ学環」では、未来を切り拓くための分野横断型教育を提供します。一拠点総合大学ならではの特長を生かし、経営・法・現代社会学部が連係する「学環」で、幅広い知識を修得。学部や学環を越えた学びを通じて多様な仲間と出会い、視野を広げます。また、京都という伝統と革新が交差する地で、地域や世界を舞台に社会・産業界と連携。起業家や海外ビジネスの現場に触れ、「起業家100人との出会い」を目標に、刺激的な経験を提供します。さらに、少人数制の伴走型教育を通じて「自走」の力を養成。ビジネスコンテストや起業活動に挑戦し、成功と失敗を分析して、自らの“不足”に気づき、自己をアップデートする姿勢を身につけます。
*2026年4月開設予定、仮称・設置構想中。学環名等、掲載内容は変更になる場合があります。